
どうも、nickです。
木曜の音楽レビューの時間です。
今回紹介する楽曲は以下になります。
今回はミロスラフ・ケイマルの演奏する、ネルーダのトランペット協奏曲変ホ長調について紹介します。(トラックの20〜22)
演奏者の紹介

ミロスラフ・ケイマルはチェコのトランペット奏者で、元チェコ・フィルハーモニー管弦楽団の首席奏者だった方です。
日本においては、ジブリ映画『ハウルの動く城』で聴かれるフリューゲルホルンのソロを担当されました。
チェコ・フィルというとnick的にはもののけ姫の演奏が頭に浮かびます。
オススメのCDです。

アレシュ・バールタはチェコのオルガン奏者で、チェコの主要な交響楽団と室内管弦楽団のソリストとして出演しています。
作曲者の紹介

ヨハン・バプティスト・ゲオルク・ネルーダ(Johann Baptist Georg Neruda)はバイオリニストおよび指揮者として活躍された古典派初期の作曲家。
1750年に最初にバイオリニストになり、その後、1772年に引退するまでドレスデンのオーケストラのコンサートマスターを務めました。
残念ながらこれ以上のことはあまりわかっていないようです。
トランペット協奏曲でも有名なハイドンの20歳ほど年上になります。
楽曲について
そんな彼が書き残したいくつかの曲のうちの一つが、このトランペット協奏曲になります。
伝統的な「急、緩、急」の3楽章形式の協奏曲ですが、少しひねりのある楽曲になっています。
本来はコルノ・ダ・カッチャのために書かれた曲になります。
ホルンとコルネットのご先祖様にあたる楽器です。

実際にコルノ・ダ・カッチャでネルーダを演奏している動画。
本来は弦楽合奏による伴奏ですが、このCDではオルガン伴奏を演奏しています。
1楽章
古典派時代の協奏曲によくある長めのイントロからの演奏。
幅の広い跳躍が少なく、流れるようなエレガントな旋律がいいです。
そして、トランペットの輝かしい音!
こういうトランペットになりてぇ〜(´。`)
2楽章
緩徐楽章。
この楽章だけでなく、3つの楽章すべての曲の終わりにカデンツ(無伴奏のソロパート)があるのも、この協奏曲の特徴であります。
弦楽器奏者ならではの発想なのだろうか?
3楽章
3楽章がやや変わった構成になっています。
1つはかなりテンポの早い楽章になることがおおいですが、ネルーダの3楽章はそこまでテンポが早くありません。
(4分音符120程度)
また、2拍子であることが多いですが、3拍子になっております。
1楽章のモチーフが使われているのも特徴の一つです。
3楽章のテンポが抑えられていることによって、曲全体の優雅さが際立つようになっています。
ネルーダはちょうどnickが今練習している曲になります。ハイドンやフンメルのものと比べるとやや地味な印象ですが、独特の優雅さがハマり、個人的に取り組んでいます。高校生や大学、社会人であれば十分に練習していける難易度だと思います。この記事をきっかけに取り組んでいただけたら幸いです。

いかがだったでしょうか?
週末に旅の写真の紹介、月曜には書籍のレビューをしております。
よろしければそちらもご覧ください。
ツイッター、インスタグラムも宜しくおねがいします。
( `Д´)/ジャマタ
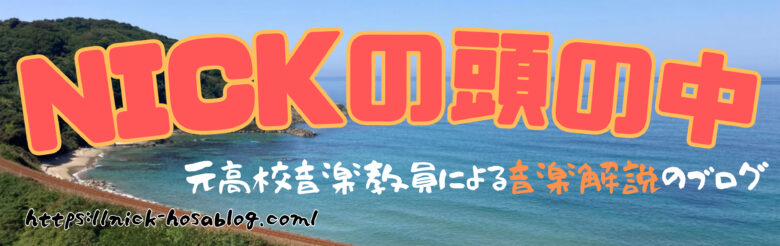

コメント